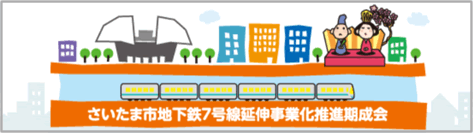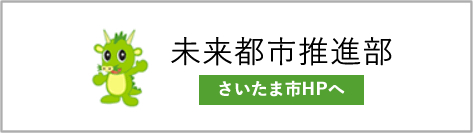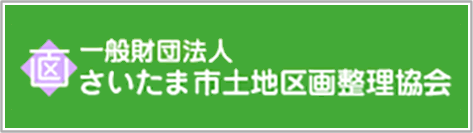岩槻といえば?
-
言わずと知れた人形のまち
 五月人形
五月人形
 おひなさま
おひなさま
岩槻は日本有数の人形生産地。日光東照宮の造営に携わった工匠たちが、岩槻に留まり人形づくりが始まったといわれています。多くの人形師が技法の向上に努め、岩槻の「岩槻人形」と「江戸木目込人形」は経済産業大臣から伝統的工芸品に指定されています。
-
花いっぱい、緑いっぱい
 岩槻城址公園
岩槻城址公園
 朝顔市
朝顔市
岩槻には花と緑がいっぱい。春はサクラ、夏にはアサガオ、秋はコスモスと、四季を通じてお花も楽しめちゃいます。区内を流れる元荒川や緑のトラスト保全第7号地に指定された雑木林など、森林浴しながらの散策にもってこいの憩いの場も。
-
農業が盛んでグルメがてんこ盛り
 ヨーロッパ野菜
ヨーロッパ野菜
 岩槻グルメ
岩槻グルメ
都心に近い岩槻。ですが、農業が盛ん。近年話題になった、若手農業家が作る色鮮やかな「ヨーロッパ野菜」や、イチゴや小松菜、トマトに梨に、こだわりの卵だってあります。くだもの、新鮮な野菜をたっぷリ使ったグルメ、堪能~!
-
歴史と城下町の雰囲気が残るまち
 岩槻藩遷喬館
岩槻藩遷喬館
 時の鐘
時の鐘
歴史好きにはたまらない、見どころ満載の岩槻。城下町の風情が残る小道を歩いたり、神社仏閣を巡ったり。いくつも残る文化財は、城下町岩槻を物語ります。歴史が生活の中にとけ込んでいるのは、まさに岩槻ならでは。
岩槻人形博物館

「岩槻人形博物館」は、日本有数の人形産地として知られるさいたま市岩槻区にオープンした人形をテーマとする日本初の公立博物館。日本画家で人形玩具研究家の西澤笛畝(にしざわてきほ・1889~1965)が収集したコレクションを中心に5,000点以上の人形に関する資料を所蔵しています。
岩槻人形博物館:
https://ningyo-muse.jp/
にぎわい交流館いわつき

「にぎわい交流館いわつき」は、岩槻の新しい魅力を創造・発信する拠点です。地域の歴史や文化を学び、さまざまな製作体験ができます。岩槻土産や地元産のヨーロッパ野菜を使った「ヨロ研カフェ」も人気。
にぎわい交流館いわつき:
https://www.nigiwai-koryukan.jp/
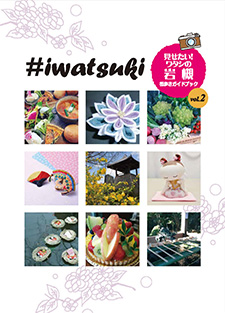
便利な岩槻周辺マップ集
様々な目的に合わせたマップを用意しました。街歩きや生活にお役立てください。
-
一日たっぷりまち歩き編
 PDF(日本語)ダウンロード
PDF(日本語)ダウンロード
-
体験・お買い物編
 PDF(日本語)ダウンロード
PDF(日本語)ダウンロード
-
生活便利マップ
 PDF(日本語)ダウンロード
PDF(日本語)ダウンロード